ECLの初代社長、高井太郎さんは帝国海軍出身でした。彼の活躍が【二宮隆雄著、駆逐艦 雪風 (幻冬舎文庫)】に描かれていますのでご紹介します。8月は終戦の月です。過去に思いをはせ、今を考えるのも良いと思います。もし、ご興味を持たれましたら、是非、お買い求め下さい。
駆逐艦 雪風 南太平洋の激闘より
もう一つ画期的な装備が雪風に備えられた。
逆探というレーダーの逆探知器(アンチレーダー)であった。
アメリカのレーダーは、昭和十七年中頃から性能が向上していた。
レーダーによる発見距離は最低二万メートル、ときには三万メールの遠方から、日本艦隊をキャッチした。
だが見張員の肉眼による距離は、最高でも一万メートルである。
この二倍以上の差は、夜戦においてアメリカ艦隊を有利にさせた。
日本軍の逆探は、アメリカ軍のレーダーに対抗するために発明された新兵器である。
原理はレーダーが発信した電波を、遠方からスクリーンでとらえて、敵艦の方向を測定する。
この逆探の第一号が雪風に取り付けられた。
逆探一号装備の栄誉は、海軍内に雪風は、“不沈艦”という信頼が浸透していたからではなく、激戦地に赴く駆逐艦で、逆探が正確に作動するかどうか、早く確かめたかったからである。錯誤なく識別能力が働いて、敵艦撃沈の一助となるよう願いが込められた。
このとき雪風の通信士は高井太郎中尉(海兵七十期)であった。
高井は測量士として巡洋艦古鷹に乗り組み、昭和十七年のサボ島沖海戦で、同艦が沈没して救助されたのち、十二月に雪風に赴任した。
「逆探一号装備とは、縁起がいいな」
高井は逆探装備の報せに、胸を躍らせた。
思えばサボ島沖海戦で、暗夜の豪雨の中、古鷹の艦橋の士官が全く予期せぬときに、敵のレーダーによる一斉射撃を浴びせられて、沈没した苦い経験がある。
暗夜に敵の存在を知ることのできる逆探という新兵器に、高井は期待を大きくした。部下とともに呉で技師から逆探操作の講習をうけて、実践で使用すべく備えた。
六月十六日。二十五ミリ機銃を増設して新装なった雪風は、トラック島に向けて出撃した。高井が逆探を使う機会は、七月にやってきた。
七月十二日。陸軍の第四十五連隊第二大隊と、砲兵一個中隊を、コロンバンガラ島に緊急輸送する命令が下された。
雪風は二水戦の宮崎少将率いる警戒隊に属して出撃した。
駆逐艦三日月を先導に、機関軽巡神通が続き、雪風の後方に四隻の駆逐艦が単縦陣追走する。
日本海軍はニューギニアを制圧した連合軍とのあいだで、ソロモン諸島近海において日夜激闘をくり返していた。
コロンバンガラ島近海は、ガダルカナルの航空部隊の攻撃もあるが、敵艦隊との遭遇の可能性も高かった。
艦橋に立つ高井は、逆探を操作する部下を信頼して、受話器を耳に当てていた。敵のレーダーは二、三万メートル前方から、味方の艦の位置と距離を測定できる。逆探はレーダー音波を発した敵艦隊の存在と方向は察知できるが、距離は測れない。
アメリカ軍のレーダーと、日本軍の逆探に科学的能力の差はあるが、戦は機械だけで勝敗が決まるものではない。
高井は敵のレーダー音波を、発信と同時にとらえる自信があった。
敵艦の存在と方向さえわかれば、迷うことなくその方向に突き進む。あとは世界に誇る見張員の三・〇の視力で敵艦を発見し、水雷長と砲術長の腕に任せて撃沈する。
漆黒の海を進撃する警戒隊と輸送隊九隻の中で、逆探を備えているのは雪風一艦である。
高井の責任は重かった。だが敵艦隊のレーダー音波を早期に逆探できれば、夜戦は有利に展開できる。
二十二時五十七分。敵艦の発したレーダー音波を、ついに逆探がキャッチした。
「直進方向、敵レーダー波あり」
部下の通信員から高井に連絡が入った。
高井が勢い込んで菅間艦長に報告する。
「敵レーダー波キャッチしました。直進方向です」
「おお。そうか」
冷静でポーカーフェイスの菅間の顔が、コンパスの光を映して紅潮したように見えた。
各館に連絡した菅間は三十ノットに増速した。
「砲雷撃用意せよ」
雪風はすぐさま戦闘態勢に入った。
大役を果たしてホッとしている高井は斎藤水雷長を見た。
水雷長として初陣の斎藤は、高井が逆探した敵艦影が見えるのを、水雷長用の大きな双眼鏡ごしに凝視している。
雪風は雷撃戦からしばらく遠ざかっている。
水雷科員は手ぐすねひいて、雷撃戦を待ち望んでいるはずだ。
斎藤はこの好機を逃してなるものかと、体が奮える思いで双眼鏡の先を見つめた。
二十三時三分。雪風の見張員が敵艦影を発見した。
「敵艦発見。前衛らしき艦隊」
斎藤の双眼鏡も敵艦をとらえた。前衛艦の背後に本隊らしき艦がいる。
二十三時八分。旗艦神通も敵艦を発見した。
このとき神通の伊崎司令官のとった行動は、己を犠牲にした大胆不敵なものだった。
距離六千で敵艦隊を照射して、戦闘を開始した。
雪風からも神通の照射で、敵艦隊がはっきり見えた。
雪風以下駆逐艦五隻は、照射された敵に三十ノットで突撃した。
すでに魚雷攻撃範囲に入っている。九三式酸素魚雷は五十ノットで二万メートル届く。一万メートルを切ればかなり高い命中率になる。
斎藤は近づいてくる敵艦を見た。
「撃たせて下さい。撃たせて下さい」
と連呼した。
だが、菅間艦長は魚雷発射を許さない。
このとき菅間の横に立つ第十六駆隊の鳥居司令は、魚雷の最も高い命中率を四千メートル以内と考えていた。
水雷隊司令として老練な鳥居は、若い水雷長が酸素魚雷の威力を過信して、遠方から発射しすぎて、せっかくの高性能魚雷を無駄にした例を多く知っている。
鳥居は菅間を振り返った。
「艦長。どのあたりで撃つ」
菅間も歴戦の水雷屋である。
「四千以内で八発八中にしましょう」
「うむ」
鳥居がうなずいた。雪風は猛進していく。
菅間は探照灯をつけた前続艦の神通に、敵弾が集中するのを唇を噛みしめて見ていた。
伊崎司令官は自艦を犠牲にして、敵艦を照射し続けて、味方の攻撃を万全にしようとしている。
<どんなことがあっても、雷撃を成功させねばならない>
敵艦との距離が三千になった。
鳥居司令が大きくうなずいた。
それを見た菅間が、
「取舵いっぱい」
を下命した。
左に回頭した雪風は、敵への、魚雷の射角を得た。
斎藤はこの一瞬を待っていた。
肚の底から声をしぼり出して下命した。
「発射はじめ」
八本の魚雷が海中に消えた。無気泡で敵艦に接近していく。
命中の期待を込めて、双眼鏡を見やりながら、次発装填を命じた。
魚雷発射を終えた雪風は、左に反転して北上していく。
菅間は左旋回できない神通を見た。
照射した神通に命中弾が多く、数ヶ所から火焔が噴き上がっている。だが砲台は射撃を止めず、敵艦隊に向かって砲撃を続けている。
菅間は熱いものを胸に感じながら、双眼鏡を敵艦に向けた。
まもなく魚雷が到達するころである。
斎藤が命中時間をストップウォッチで測っている。
「用意。てーっ(撃て)」
斎藤の興奮した声の直後に、大きい二本の火柱が敵艦の中央に上がった。
火焔が噴き上がった。直後に轟音が聞こえた。
「命中!命中!」興奮した見張員の声が、艦橋に響き渡った。
艦橋の全員が歓声を上げた。
「命中だ。万歳!」
魚雷を発射した水雷科員も万歳を三唱した。
だが喜びにひたってはいられない。
次発装填を急がねばならない。
予備魚雷が甲板に運ばれていれば、次発装填は五分でできる。
だが戦闘状況のために、艦内の格納庫から運び上げて装填しなければならない。この作業はおよそ二十分が見込まれる。
河口は格納庫のドアを開けて、四本の魚雷にワイヤー装填索を取り付けた。
雪風めがけて敵の砲弾が飛んでくる。感が激しく傾斜して、次発装填作業がはかどらない。一分でも早く装填できれば、ふたたび反転して撃沈できる。
「まだか。まだか」
艦橋の斎藤からの、矢のような催促を、伝令が何度も口にする。
河口たち水雷科員は、焦らずに仕事を進めた。雪風の水雷科員の闘魂は、どの駆逐艦にも負けない。
魚雷の手入れは三日に一度で十分であったが、河口たちは毎朝丹念に検査した。
それは上からの命令ではない。河口たちにとって九三式酸素魚雷は自分の分身である。世界に誇れる魚雷を、一日たりとも放っておけなかった。
毎朝綿密にジャイロの調整をして、各部の点検を行ない、大切に磨いて保管した。
日頃の猛訓練に支えられた水雷科員の仕事にぬかりはなかった。
全速力で波濤を切り割って激しく動揺する甲板に、敵の機銃弾が跳弾となって、危険きわまりない。だが平常心で次発装填を十八分で終了した。
二十三時五十七分。雪風は距離一万六千で、反転する敵艦隊を発見した。
その直後スコールが来襲して、これを利用してさらに接近する。
スコールを抜けた。敵の照明弾が頭上で炸裂した。そのとき距離は約六千。斎藤が意気込んで下命した。
「発射はじめ」
八本の魚雷が海中に消えた。
十六本全ての魚雷を発射できた安心感で、河口は体の力が抜けたように感じた。
狙いは誤らずに、敵の中心部隊から、数本の火焔が見えた。
魚雷を撃ち終えた雪風は、戦場を離れた。砲声がしだいに遠くなる。かわって波音が聞こえて来た。
河口は興奮のあとの虚ろな気持ちで甲板に立っていた。
逆探が功を奏したコロンバンガラ沖夜戦で、日本艦隊は勝利した。
だが、勇猛果敢に照射を行った軽巡神通が沈没した。
アメリカ軍は巡洋艦三隻が大破して、駆逐艦一隻が沈没した。
警戒隊の奮闘に守られて、輸送駆逐艦は千三百余名の陸軍部隊を、コロンバンガラ島に無事陸揚げして作戦は成功した。
あとがきより
だが一つだけ言えることは、昭和二十年八月十五日の敗戦をもって、それ以前の日本と日本民族のすべてを否定すべきではない、ということだ。
戦争は悪の行為である。しかし当時、祖国を救うことを信じて戦った多くの純真な青年がいた。彼らは命を捨てて父や母や兄弟や、これから生まれてくる人々を護るために戦った。
駆逐艦雪風も、そういう純真な乗組員によって戦われ、不沈のまま敗戦を迎えた。彼らの純粋な祖国愛までも否定すべきではない。
この小説を書くにあたり、私は雪風の多くの乗組員の方々にお会いした。
雪風は不沈艦であったために、ほとんどの方が生き残り、戦後の日本の復興に力を尽くされた。今も各分野でご活躍されている方も多い。
お会いした方々の記憶は、じつに鮮明であった。死を前提にした貴重な青春の一日一日を精いっぱい生きたからであろう。
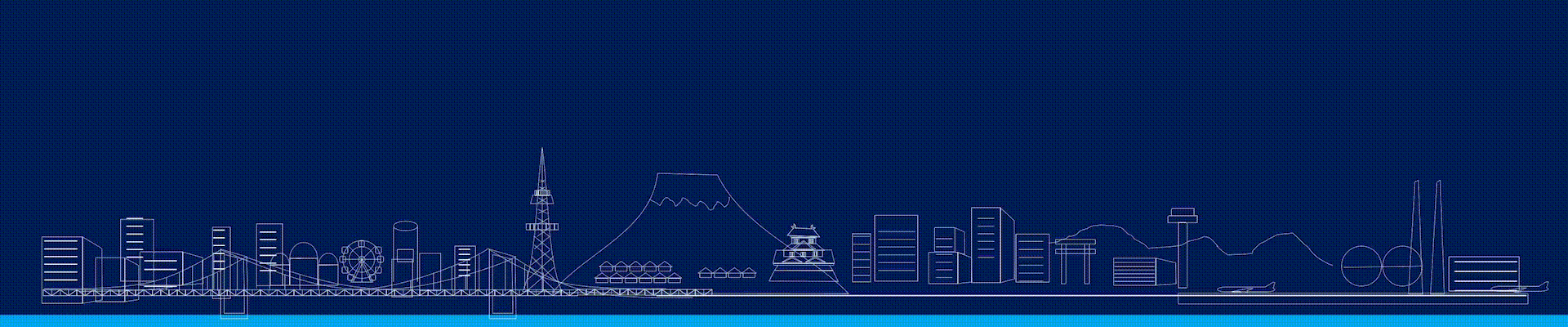

Login to comment
サインイン